

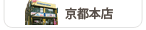
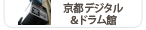
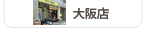
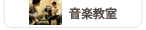
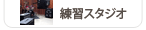
|
|
フルート よくあるトラブル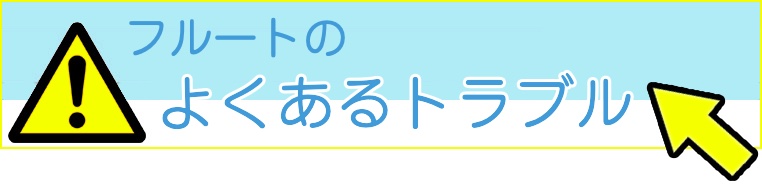
フルートのよくあるトラブル
保証書について
■頭部管/足部管がスムーズに抜き差しできない
綺麗にホコリなどを取り除いて下さい。クロス等でジョイント部分を拭き取るだけではありますが、このときに使用するクロスは表面が毛羽立ちにくいものなど、ほこりの出にくいクロスをお勧めします。
そして、入れるのですが、重要なこととしては「まっすぐ」「無理をせず」差し込むことです。
野外練習をしたときは必ず掃除をしてから楽器を組み立ててください。接合部はホコリ1つで傷がついたり、それが大きな致命傷となり抜けなくなることもあります。 少し斜めに入れてしまった程度でも管が歪んでしまって動かなくなることがあります。まっすぐ入れるということは重要なポイントですが、まっすぐ入れるにもかなり慎重にならないといけないということです。必要以上に回したり、ガタガタさせながら入れることも勿論ダメです。入りにくさを感じられた場合に、このようにされる方がおられますが入れにくい場合にはまずは無理には入れず一度嵌合部分を掃除しましょう。
原因 上記で解決しない場合には既に何らかの負荷がかかって変形してしまっている可能性もあると思います。こうなってしまったら、技術者にお願いして嵌合調整を行うしか手がありません。方法としてロウを塗るなどの手立てが無いわけではありませんが、まずおすすめはいたしませんので、ここではあえてそういった方法はご紹介しません。
▼技術者の修理
またその後軽く熱するしたりすることで外側の径を広げたりホコリや汚れ自体の状態を変化させます。その後引っ張ります。抜けるまでこの繰り返しです。
場合によってキイなど邪魔になるパーツは全て外してしまえばその部分にも力がかけられますので、そういうところでも技術を持った者が行うのと、全然違うことがお分かりいただけると思います。
■バネが外れた
反射板の位置
頭部管の内部には反射板という円形の板があり、その位置によっても音程が変化致します。
冬期以外では頭部管を主管から3〜5mmくらい(夏期では5mm~8mm程度)抜いた状態にすると音程が合いやすいですが、楽器全体の音程が高くなり過ぎる場合は頭部管を抜き、音が低い場合は頭部管を深めに差し込みます。音程が高いからといって抜きすぎるとさらに音程が合わせにくくなりますので、目安として10mmまでとして下さい。とはいえ、そこまで抜かないとまだ音程が高いという場合は、息の入れ方や構え方が安定していない可能性もありますので、吹き方を今一度見直す必要もあるかもしれません。息のコントロールができていない状態はもちろんですが、力んだ状態で演奏したり、息の入れる角度が適切でない場合は音程が合いにくい傾向にあります。
チューナーの設定 適切なチューナーの設定をしておらず、音程が合わない、合っていないと勘違いされている場合があります。チューナーのHzの設定値は440Hz~442Hzが一般的です。例えば吹奏楽では442Hzに合わせる事がほとんどですが、バロック音楽など演奏する曲によって変わります。管楽器の特徴として気温が暑くなると音程が高くなり、気温が低くなると音程が低くなる傾向にありますので、夏場などの暑い時期は442Hz、冬場などの寒い時期は440Hzで設定することも稀にあります。 一般的にチューニングで他人と合わせる時に使用する音についてはヘルツ数同様場面によって変わることがあり、例えば、オーケストラではA(ラ)、吹奏楽ではB♭(シ♭)で確認したりします。例えばフルートを吹奏楽で吹く場合、チューナーの設定を442Hzにし、運指をシ♭(左手の親指<ブリチアルディキイ>+人差し指)で音を出し、チューナーの表示がB♭(A♯)になっていることを確認しチューニングするといったような感じです。管楽器の殆どは楽器と吹き方で調整できますが、ピアノなど一部楽器はその場で調律できませんので、変えられない楽器にヘルツ数を合わせてチューニングをすることもあります。
■音が鳴らない/鳴りにくい
・高音が鳴りにくい 高音全体が「鳴らない」「鳴らしにくい」場合には、息のスピードが足りていない可能性があります。初心者にとって一番綺麗に慣らすのが難しい音域です。頭部管の角度や息の入れ方でも影響します。本来の高音ではなく、オクターブ下の音が鳴ってしまう場合や一瞬音が鳴ってもすぐに下がってしまうときは息のスピードが足りなかったり、維持できていなかったりします。また、頭部管を内側/外側へ極端に傾けすぎている可能性もあります。頭部管の角度は教本、または各ブランドで基準の構えがありますので必ずご確認下さい。フルートにはサックスやクラリネットなどの楽器のようにオクターブキイというもので高音に切り替えができるキイは存在しません。よって、息で音の高さをコントロールする楽器です。低音には低音の吹き方、高音には高音の吹き方があります。そこは要練習ですね。
・低音が鳴りにくい 上記の「高音が鳴らない」とは逆に、息のスピードが速すぎると低音が一発で出しにくくなります。また、頭部管の角度が外側になりすぎている状態でも低音は鳴りにくい状態になります。息のスピード感ですがあったかい息をゆっくり流すようなイメージで演奏すると鳴りやすくなるかと思います。この部分についても練習の必要があります。
・特定の音だけが鳴りにくい 構造上、トラブルが起きやすいキイ、鳴らしにくい音が存在します。組み立ての際にひっかかりやすい場所などもありますよね。 ・出ない音のキイが本来の動作で動いているかを確認して下さい。その前後の音が演奏できるか確認して下さい。その状況によって原因が特定できる場合もあると思います。 ・パッド(タンポ)は普段ちゃんとお手入れしているでしょうか。クリーニングペーパーで水分をしっかり取るお手入れは何気ないお手入れではありますが、日々の積み重ねで結果タンポがベタベタになってしまった時点で手遅れになることもあります。梅雨の時期などの湿気によっても貼りつきやすかったりなどもあります。鳴らない音に関連するパッドにパウダーペーパーを使用し状態を確認してみて下さい。但し、頻繁に使用することはお勧めしません。また、改善されたとしても一時的であればパッドの交換が必要な状態かもしれません。 ・衣服などに特にひっかかってしまいやすいキイ...G#キイ ・組み立て時にうっかり歪ませてしまいやすいキイ...LowC#キイ ・なお、Eメカニズムが搭載されていない楽器は2オクターブ上のミは構造上鳴らしにくい音になります。
・連動(キイバランス)の崩れ 連動が崩れている部分があるかもしれません。まずはキイの後ろに貼ってある軟物(フェルトやコルク)が剥がれていないか、劣化して潰れていないか確認してください。ネジが緩み、連動の崩れている可能性がありますが技術者でなければなかなか見つけにくいと思います。1つずつの運指を確認し、動くべきパーツがちゃんと動いているか、またそれによって音孔が閉まっているか、隙間がないかを確認して下さい。隙間があれば息漏れによって音が鳴りにくいことが考えれます。またパッド(タンポ)の表面が破れていないか、パッド自体が固くなっていないか確認してください。1、2年調整せずに使用しているとすればネジ緩んだりタンポが劣化していると思われますので、1箇所だけではなく全体の少しずつの状態の崩れによって特定の箇所だけに異常が発生している場合もあります。故障までいかずとも技術調整を必要とする状態でありメンテナンスに出す必要があると思われます。
・バネ外れ 上記「■バネが外れた」項目をご確認下さい。
・キイ歪み フルートのキイは衣服に引っかけやすく、また組み立ての際にキイのついている部分をもって組み立ててしまっていたり、お手入れをしている最中など、無意識のうちにキイを曲げてしまっていることも多いです。キイを曲げてしまうとキイの動作の連動が崩れたり、連動する部分に隙間が出来てしまいキイのタッチ感が悪くなってしまうことがあります。(この隙間をアソビと呼びます。) アソビについては楽器の構造によって作らなければならない部分や音に影響しない部分もあるので一概に悪いことではないですが、基本的にフルートはアソビを作らないのが一般的です。また、他のキイや管体に不必要な接触を起こしてカチカチとノイズが出ることもあります。キイが曲がってしまっている場合は技術者による修理が必要となります。
バネの確認
☆フルートのバランス調整について フルートの修理/メンテナンスで実際に最も必要とされる内容がキイのバランス調整。 木管楽器の中でも特に繊細でキイバランスの狂いやすいフルートは修理/メンテナンスのご依頼数も多いです。 バランスが崩れていると部分的に音が出にくくなり、キイをたくさん押さえるような低い音ほど鳴りにくくなってしまいます。 逆に言うと、しっかり調整された精度の高い楽器は最低音までのびのびとしっかり鳴ってくれます。 故意に壊していなくても日々のお手入れや組み立て、環境変化によって楽器のバランスが少しずつ崩れ、気が付くと新品の時より鳴りにくくなっていた…ということも。
修理を学んでいない方が自身で楽器を分解したり修理調整をしようとすると必ずと言っていいほど故障につながりますので、音が出にくくなったと感じたらまずはリペアマンにご相談下さい。 仮に自分で直せた!ということがあっても同時に別の不具合を起こしてしまっていたり、それ以降も何かあれば自分で直そうと思ってしまう危険性があります。 どんなに小さくゴミのようなパーツでも重要な部品であり修理時にも大いに役立つものですので安易に取れたからといって捨てたりしないで楽器と一緒に丁寧に保管・持ち込みして下さい。
弊社では修理/メンテナンス時だけでなくお客様へ新品のフルートを出荷する前にも下記のような内容でバランスの調整を行っています。
▼調整手順 足部管 ・右手小指のローラーを単独で押した時にLowCキイとC♯キイが同時に閉じるかをチェックし、キイの角度を変えることでバランスを調整します。 C♯キイが先に閉じる状態だと、ドの音程がわずかに高くなったりどうしても鳴りにくくなります。 LowCキイが先に閉じる状態だとドの音がしっかり鳴らず音がひっくり返ったりしますが、保険としてC♯キイのレバーを同時に小指で押さえることでちゃんと鳴るようにできていますので、どちらかといえばLowCキイが閉じることを優先させてバランスを取っています。
主管 ・右手薬指のDキイと、指で直接押すことのないF♯キイのバランスをチェックし、調整ネジでバランスを取ります。 F♯キイはフルートにおいてバランス調整の要となるキイで、計3つのキイと連動していますがF♯キイにとってDキイは優先度の低いキイのため、F♯キイはほんのわずかDキイより遅れて閉じるくらいがベストなバランスになります。 ただしF♯キイがあまりにも遅いとファ♯の音が鳴りにくくなってしまいますので、あくまでもほんの少しの差です。 逆にDキイのほうがが遅いと、レ以下の音がすべて鳴りにくくなります。
・右手中指のEキイとF♯キイのバランスをチェックし、調整ネジで調節します。また、Eメカニズムがある楽器ではそれと同時にG♯キイとのバランスをチェックしてEメカの「ウデ」の角度で調整します。 EキイもF♯キイにとって比較的優先度の低いキイですので、ほんの気持ち程度F♯キイが遅く閉じるようにします。G#キイはそれよりも遅く閉じる程度にすることで他の音を邪魔することなく3オクターブ目のミが鳴らしやすくなります。
・右手人差し指のFキイと隣のF#キイのバランスをチェックし、調整ネジで調節します。F#キイに関わるバランスで最も重要な部分で、ほどんど同じタイミングで閉じる状態でなければファ以下の音の鳴りが大きく変化します。 そのあと離れたところにあるB♭キイとのバランスを主にキイの角度で取ります。バランス調整のためのネジはありません。ここではB♭キイの優先度が低いので、わずかに遅めに閉じる状態にします。
・左手薬指のGキイと隣のG#キイのバランスを、ほぼ同着で調整します。通常は調整ネジで行いますが、Eメカニズムが付いていないモデルでは調整ネジが無いものも多いので、その場合はキイの角度で調整します。
・左手中指のAキイと隣のB♭キイのバランスを調整ネジで取ります。ほぼ同着かつB♭キイが先に閉じないように注意します。
・左手親指、管体の裏側にあるBキイと、表のB♭キイのバランスをキイの角度で調整します。こちらもほぼ同着が理想ですが、仮にどちらかの閉じる力が弱くても他のキイバランスによってカバーできたり、
親指でしっかり押すため息漏れがしにくいところです。逆に言うとバランスの崩れに気付きにくい部分となります。 最後に試奏を行い、弱い力でキイを押さえたときでも各音がしっかり鳴るかどうかをチェックします。
|